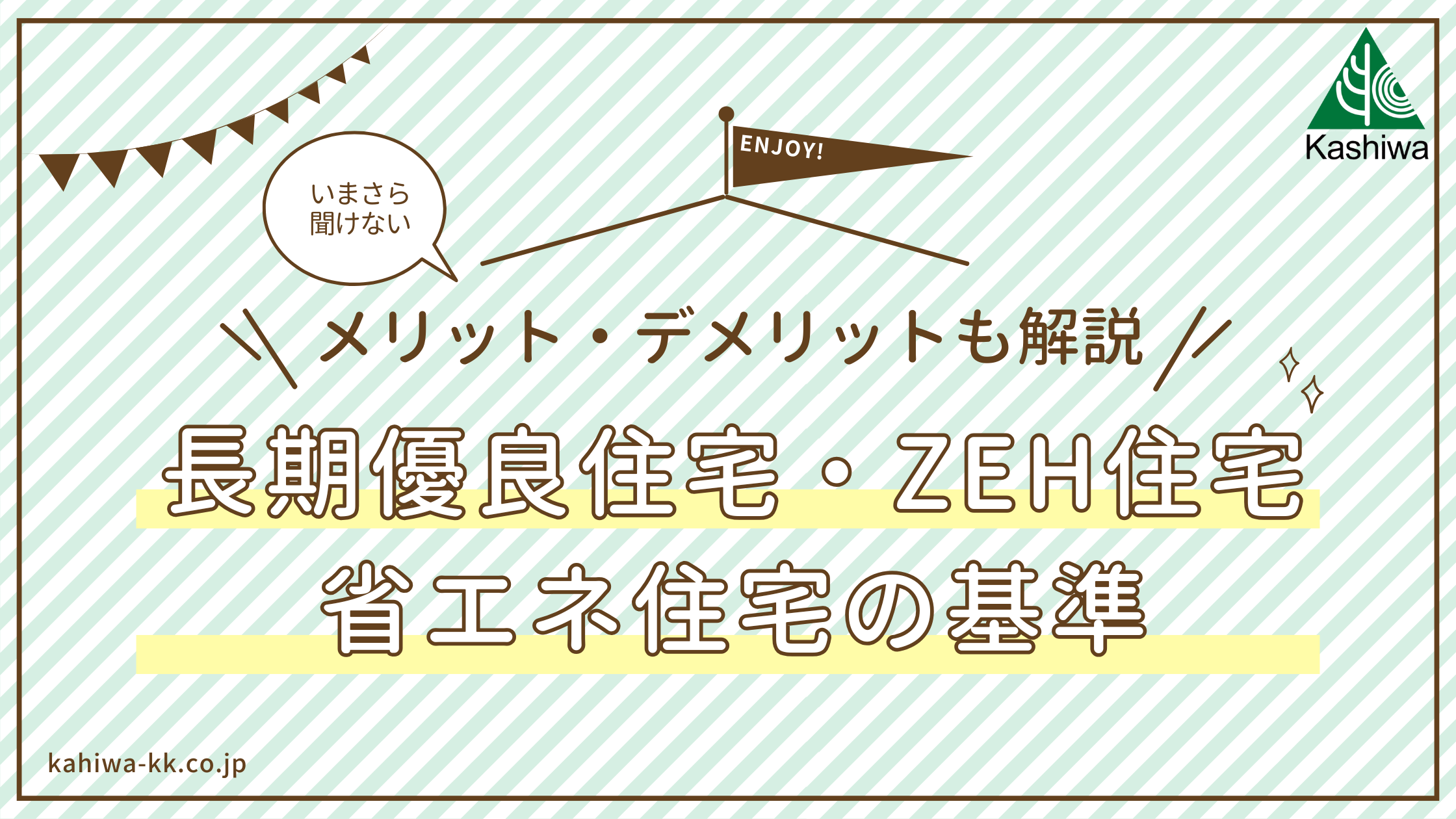これから注文住宅を建てる方も、建売住宅を購入する方も覚えておきたい家の性能。住宅ローン控除や各種補助金の対象から外れてしまわないよう、きちんと基準を理解しておくことが大切です。そこで、高性能な住宅であることを示す「長期優良住宅」「ZEH住宅」「省エネ住宅」について、それぞれの基準やメリット・デメリットについて解説していきます。
長期優良住宅とは?
住宅ローン控除の対象となる長期優良住宅。上限金額が最も高いため、ものすごく高性能で建築費用がものすごく高くなりそうなイメージがありますが、どのような住宅を長期優良住宅として認定するのでしょうか。基準や要件、どのくらいの建築費がかかるのか解説します。
長期優良住宅の定義と基準
長期優良住宅とは、2009年(平成21年)から施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たした住宅です。9項目の認定基準が設けられています。
1. 劣化対策
2. 維持管理・更新の容易性
3. 維持保全計画
4. 耐震性
5. 省エネルギー対策
6. 居住環境への配慮
7. 住戸面積
8. 可変性(共同住宅等のみ)
9. バリアフリー性(共同住宅等のみ)
認定を受けるための要件
長期優良住宅の性能値としてわかりやすい基準は、一戸建ての住戸面積は75㎡以上で「耐震等級3」「断熱等級5」「一次エネルギー消費量等級6」が求められる点です。劣化対策や維持保全計画によって定期的な点検・補修に関する計画も策定されます。
認定を受けるためには、構造等が適合するかの確認及び申請を着工前に行う必要があります。登録住宅性能評価機関に確認書等の交付をしてもらい、所管行政庁に提出します。建築主が申請する場合もありますし、施工業者が代行する場合もあるので、打ち合わせの際にしっかりと確認し、申請漏れがないようにしましょう。
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅を建てるメリットには以下のようなものがあります。
1. 耐震性・断熱性・省エネ性に優れている
2. 住宅ローン控除や住宅ローンの金利優遇を受けられる
3. 地震保険の割引を受けられる
4. 売却をする際も価値が残りやすい
性能面に優れた住宅なので、長く安心して住み続けられるほか、省エネ性能も高いので光熱費も以前までに住んでいた家より抑えられることが多いです。住宅ローンの金利優遇や減税などの金銭的メリットも享受できます。また、もし家を売却することになっても長期優良住宅は資産価値が残りやすいので、買い手が付きやすく、売却価格も相応に見込めるでしょう。フラット35の残期間を次の購入者に引継ぎすることができるといった優遇も受けられるため、特にフラット35で家を建てる方は長期優良住宅にしておくとよいでしょう。
長期優良住宅のデメリット
長期優良住宅を建てるデメリットは、建築費用が高くなりやすい・建築に少し時間がかかるという点でしょう。長期優良住宅を建てるためには、性能面に優れた建材と各種申請が必要です。
基準に適合するよう、構造計算や設計図書等の設計費用がやや高くなるほか、申請に必要な書類を用意するのも費用が生じます。建材もやや高くなるため、建築会社によってはオプション費用が生じる可能性もあるでしょう。また、申請後の書類精査時間もかかるので、着工まで期間が空くことも想定されます。
昨今では性能の高い建材を標準仕様とするメーカー・工務店が増えてきているため、追加費用が多くなるとは限りませんが、よく見積内容を確認するようにしましょう。
ZEH住宅(ネットゼロエネルギーハウス)とは?
ZEH住宅は昨今主流になりつつあり、人気も高い省エネ住宅です。よりエネルギー消費量の削減や創エネルギーに力を入れた住宅で、長期優良住宅と同様様々な優遇を受けることができます。
ZEH住宅の定義と基準
ZEH住宅(ネットゼロエネルギーハウス)は、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」のことです。
かみ砕くと、「断熱性能を高めてくださいね」「省エネ性能の高い空調等を導入してくださいね」「再生可能エネルギー(主に太陽光発電システム)を導入してくださいね」「これらによって消費するエネルギーと創るエネルギーを±0に近づけましょう!」といったイメージです。つまり、断熱性や省エネ性が優れている家に、発電設備を付けたものがZEH住宅となります。
今後2030年をめどに、ZEH住宅が標準の基準となっていくことが見込まれています。2025年4月からは省エネ住宅が最低基準となりますが、今から建てるのであればZEH基準を満たす住宅を建てておく方が長い目で見て安心です。
認定を受けるための要件
ZEH住宅の認定を受けるためには、主に「断熱等級5」「一次エネルギー消費量等級6」「太陽光発電」を備えた住宅であることが必要です。省エネ住宅や長期優良住宅と同様に、認定を取得することで住宅ローン控除や補助金などの税制優遇措置も受けられる場合があります。
ZEH住宅にはいくつかの階級があり、地域特性によって緩和措置があります。まず、「Nearly ZEH」です。Nearly ZEHは、寒冷地や多雪地域であまり多くの日射が見込めず、太陽光発電で賄いきれないと想定される場合に適用されます。Nearly ZEHでは太陽光発電の設置が免除される可能性があり、消費エネルギー量も±75%以上削減で良いという基準緩和がなされています。もう一つは「ZEH Oriented」です。ZEH Orientedは住宅密集率が高く狭小地の多い都市部などに適用されます。狭小地では屋根の面積も小さく、載せられる太陽光パネルが少なくなるため発電量が見込めません。そのため、太陽光パネルの設置が免除され、省エネ率20%を超えると適用されるのがZEH Orientedです。
ZEH住宅のメリット
ZEH住宅には多くのメリットがあります。まず、一つ目は光熱費の削減です。再生可能エネルギーを利用し、エネルギー消費を抑えることで、光熱費が大幅に低減されます。二つ目は快適な住環境です。断熱性能が高いことにより、室温が安定し、季節を問わず快適に過ごせます。三つ目は経済的メリットです。住宅ローン控除や補助金などの経済的メリットも受けることができます。
ZEH住宅のデメリット
ZEH住宅のデメリットは、初期の建設コストが高くなることが挙げられます。高性能な断熱材や省エネ設備、再生可能エネルギーシステムを導入するために、一般的な住宅と比較してコストが増加する傾向があります。また、認定のための手続きが煩雑で、専門の知識が必要となることから、時間と労力がかかります。さらに、再生可能エネルギーシステムのメンテナンスや交換が必要になる場合もあり、長期的な維持費用も考慮する必要があります。
太陽光パネルの設置費用は10~15年ほどで光熱費の削減分+売電収入で回収することができますが、太陽光パネルのメンテナンス費用(足場設置や屋根の補修等も発生する)がかかることは念頭に置いておくとよいでしょう。
省エネ住宅の種類と特徴
省エネ住宅は、2024年現在、住宅ローン控除を受けることができる基準となる住宅です。今後さらに住宅性能基準が高まっていくことが想定されているため、少なくとも省エネ基準をクリアする住宅を建てておく必要が出てきます。
省エネ住宅の定義と基準
省エネ住宅とは、エネルギー効率に優れた設計と設備を持つ住宅のことを指します。必要な性能は断熱性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上です。
2025年4月以降は、この基準に適合することが新築の条件となりますので、住宅会社各社は標準仕様で断熱等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上になる建材を採用することでしょう。2030年以降はZEH水準が標準になっていくので、今から建てるという場合にはZEH水準以上の性能で建てておくことがおすすめです。
認定を受けるための要件
省エネ住宅であることを証明するには、BELS認証というラベルを発行することが必要となります。エネルギー消費量等級・断熱等級・目安光熱費が記載されるラベルで、省エネ住宅かを判断するのに必要な情報が評価されます。BELS認証には取得費用が掛かるため、諸費用部分に申請費用が加算されることになると思います。見積書の内容を確認し、認証手数料が入っているかよく確認しておきましょう。
省エネ住宅のメリット
省エネ住宅のメリットは、ZEH住宅よりもコストを抑えた家づくりで住宅ローン控除等を受けることができる点です。既存住宅よりも断熱性能や省エネ性能に優れているため、光熱費の節約効果もあるでしょう。
省エネ住宅のデメリット
省エネ住宅のデメリットは、住宅ローン控除や各種補助金の対象額が少なくなってしまう点です。資産価値としても、「より高性能な住宅」とは判断されにくいため、住み替え等で売却するときの価格も住宅ローンの残債分を回収できない可能性が出てきます。
初期コストをもう一歩積むことでZEH住宅や長期優良住宅を目指せるうえ、2030年にはZEH水準を標準としていく流れから、「今省エネ住宅を建てること」自体が非常にもったいないことなのではないかと考えられるでしょう。
長期優良住宅とZEHの違い
長期優良住宅かZEH住宅にするかという点で迷われる方もいらっしゃると思います。そこで、長期優良住宅とZEH住宅の特徴を再度まとめて比較していきましょう。
性能と基準の比較
長期優良住宅とZEH住宅はともに高性能な住宅として知られていますが、それぞれ方向性が少し違います。「断熱等級5」「一次エネルギー消費量等級6」という省エネ性能部分の基準は共通です。長期優良住宅では耐震性や劣化対策、維持点検など「長持ちさせられること」が重視され、ZEH住宅では太陽光発電など「エネルギーの自給自足率」が重視されます。
長期優良住宅とZEHの選び方
長期優良住宅とZEH住宅のどちらを選ぶかは、購入者のライフスタイルや重視する基準によって異なります。
長期優良住宅が適している人
長期優良住宅は、耐震性や長期間に渡る耐久性や安全性を重視する方に向いています。住宅ローンがフラット35やフラット50で長期優良住宅をローン会社から求められている場合や、太陽光パネルの導入に懸念がある方も長期優良住宅のほうがよいでしょう。
共働きで昼間家にいることが少ないというご家庭の場合、蓄電池を設置しないと太陽光発電の恩恵は売電収入による光熱費の抑制にとどまります。太陽光発電をそこまで必要としない場合は、長期優良住宅を取得する方が建築費用と受けられる控除・金利優遇とのバランスがとりやすいでしょう。
ZEH住宅が適している人
ZEH住宅は、省エネ性能を最優先する方に適しています。光熱費を抑え、環境に配慮した生活を送りたい方には最適な選択肢となるでしょう。ZEH住宅も住宅ローン控除や金利優遇、各種補助金の対象となります。
ZEH住宅での太陽光発電は、昼間は発電した電気を使い放題、余った分は売電という形となるので、昼間家に人がいる・ペットがいて空調をつけっぱなしという方にお勧めです。さらに蓄電池をつけることで夕方以降の電気代も節約することができます。
リモートワークやフリーランス、主婦・主夫が昼間家にいるという場合は、ZEH住宅を選ぶとよいでしょう。
今のうちから高性能住宅を建てて将来に備えよう
近年、住宅の省エネ性能や環境への配慮が求められるようになってきました。今のうちに長期優良住宅やZEH住宅を検討することには多くのメリットがあります。住宅ローン控除や補助金の恩恵を受けられるほか、税制上の優遇措置も得られます。また、省エネ性能が高い住宅は長期的に見ると光熱費の削減にもつながり、経済的にも有利です。
将来の環境変化や法規制の改定にも対応しやすくなります。将来を見据え、高効率で環境に優しい住宅を選択することを検討してみてはいかがでしょうか。